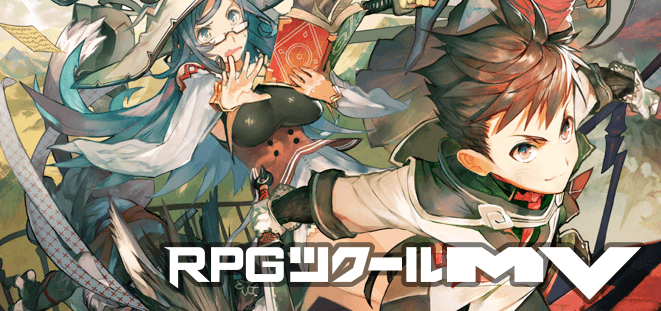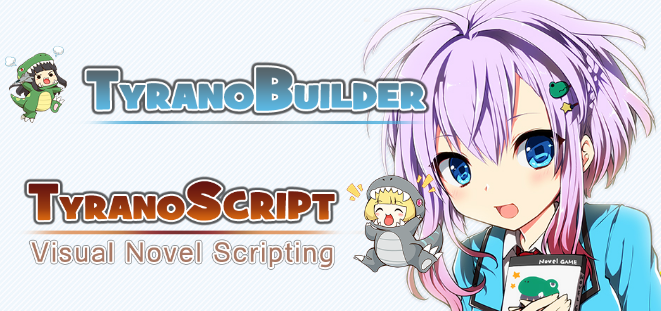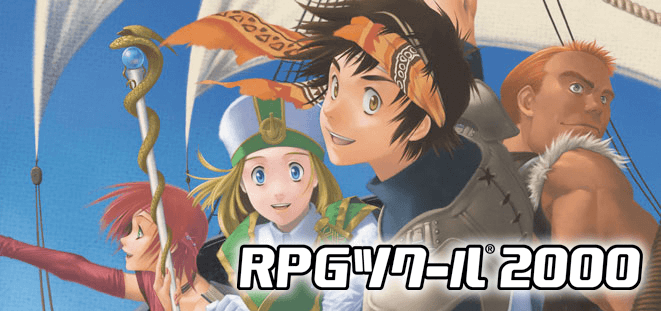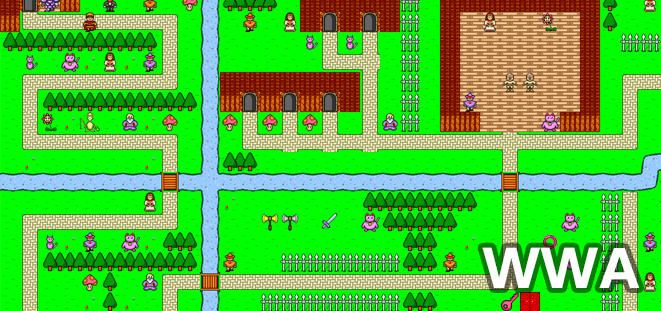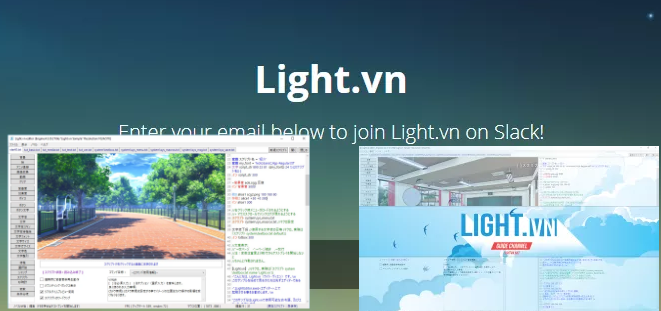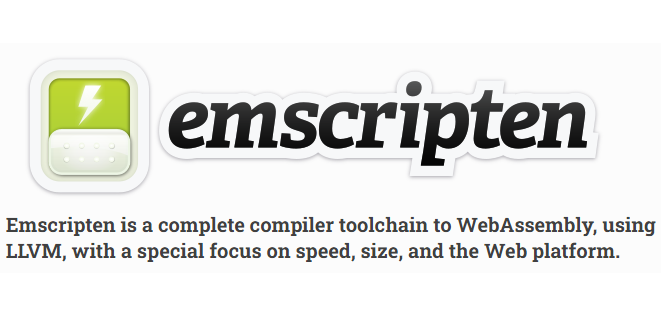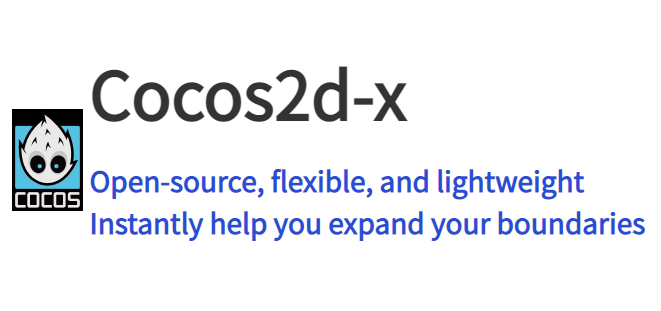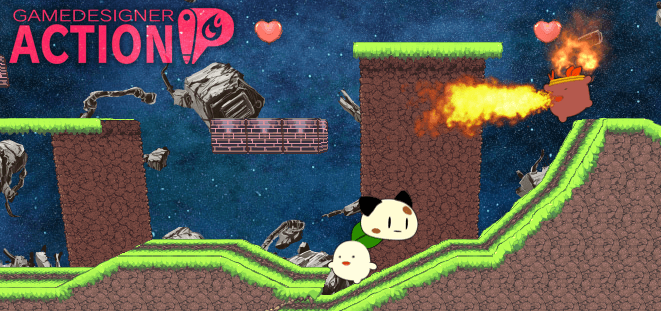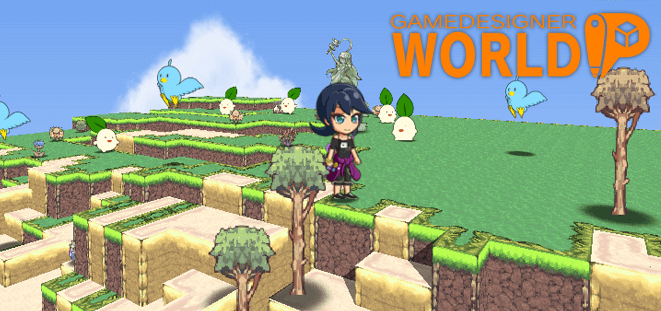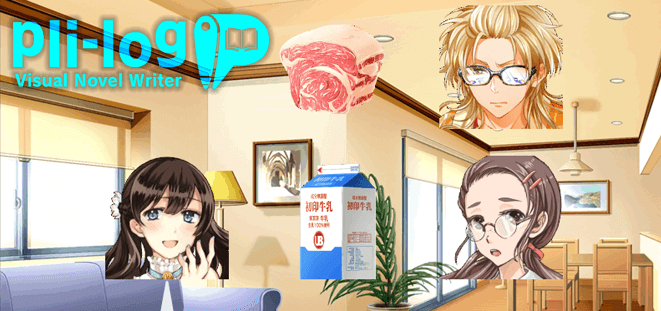- PLiCy ゲームコンテストって?
-
PLiCyゲームコンテストは、2015年からスタートした日本最大級のフリーゲームコンテストです。
昨年開催したPLiCyゲームコンテスト2024では415作品のゲームが応募されました。
PLiCyゲームコンテストではより公平・公正な審査を目指し、外部審査員様方のご協力を仰ぎながら年々審査体制を更新を行いつつ開催を続けております。
本年度も『システム部門』・『シナリオ部門』・『アクション部門』・『カルチャー&アカデミー部門』の4部門を基軸に評価を行いつつ、おもしろおかしく笑える盛り上がりを見せる作品を『KSG・バカゲー部門』として推していきます。
ぜひ、PLiCyコンテスト2025へのご参加をご検討くださいませ!
歴代コンテストの各ページはこちら:- 全コンテスト部門賞検索
- PLiCyゲームコンテスト2025 (第十一回コンテスト)
- PLiCyゲームコンテスト2024 (第十回コンテスト) / 結果発表 / 敢闘賞作品
- PLiCyゲームコンテスト2023 (第九回コンテスト) / 結果発表 / 敢闘賞作品
- PLiCyゲームコンテスト2022 (第八回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyゲームコンテスト2020 (第七回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyゲームコンテスト2019 (第六回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyゲームコンテスト2018 (第五回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyゲームコンテスト2017 (第四回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyゲームコンテスト2016 (第三回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyゲームコンテスト2015 (第二回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyゲームコンテスト2014 (第一回コンテスト) / 結果発表
- PLiCyで公開できるゲームはどんなもの?
-
PLiCyでは、Unity、RPGツクールMV、ティラノスクリプト、WolfRPGエディターといった
主要なゲーム制作ソフトで作られたゲームに対応しております。
PLiCyで対応をしている主要なゲーム開発環境は以下になります。
-
その他、外製エンジンにつきましては動作環境をご確認ください。
UnityはWebGL出力版に対応しております。
Nintendo Switchは任天堂株式会社の登録商標です。
ツクールは株式会社Gotcha Gotcha Gamesの登録商標です。
インディゲームクリエイターは株式会社デジカの登録商標です。
引用している画像の権利は、各権利者様が保持しております。
PLiCyでは、サービス内でアクションゲームやノベルゲームなどを制作することもできます。
-
- コンテストについて
-
運営プロジェクト審査員の投票によって順位が決定いたします。
投票により総合順位が決定され、 総合順位の上位から順に、「システム部門」「シナリオ部門」「アクション部門」「カルチャー&アカデミー部門」のゲームが割り振られていきます。
それぞれの部門に「金賞」「銀賞」「銅賞」があり、各部門の順位に従って割り振られます。
銅賞は部門によって複数作品に贈られる場合があります。
部門分けは基本的にジャンルから判別しますが、運営プロジェクト側で部門を変更する判断をすることもございます。
また、上記部門の他にksg・バカゲー部門がございます。
ksg部門はksgが受賞できる賞ですので、高クオリティのゲームをksgジャンルにした場合では
必ずしもksg賞を受賞できない可能性がございますのでご注意ください。
また、原則的にksg・バカゲー賞は金賞・銀賞・銅賞と重複しません。
選考の過程において、最終選考まで到達した作品をファイナリスト作品として選出、ファイナリスト賞の授与を行っています。
加えて上記の賞に該当しなかった作品についても一部を敢闘賞・準敢闘賞・カルデミー賞・KSG奨励賞として作品紹介を行っています。
- システム部門: ロールプレイング、シミュレーション、パズル
- シナリオ部門: アドベンチャー(ビジュアルノベル)
- アクション部門: アクション、シューティング、スポーツ
- カルチャー&アカデミー部門: 教養、教育、文化、歴史
- ksg部門: ksg
- スポンサー審査員特別賞: スポンサー審査員が選定した作品
- コンテストに応募するには?
-
- PLiCy に通常の手順でゲームをアップロード、もしくは作成をしてください。
コンテストに参加するためにはPLiCyへのユーザー登録、及びログインが必要になります。
非ログイン状態でのゲーム作成・投稿は作品の本人確認が行えないため、コンテストの対象外となります。
アップロード・作成のやり方については各ヘルプマニュアルをご参照ください。
ヘルプマニュアル: Unity・RPGツクールMV・RPGツクールMZ・RPGツクール2000・RPGツクールVX Ace・ティラノスクリプト・PlayCanvas・WWA Wing
ヘルプマニュアル: ラノゲツクール MV・Light.vn・HSP・HTML5
ヘルプマニュアル: WolfRPGEditor・インディゲームクリエイター・pli-log・ゲームデザイナーアクション・ゲームデザイナーワールド
フェス「公式ゲームコンテスト」を開き、応募するゲームをフェスに登録してください。
- 登録したゲームのタグに「PLiCyゲームコンテスト2025参加作品」を追加、タグロックしてください。
表記ゆれを防ぐために上記タグ内容(カギ括弧は除く)をコピー&ペーストすることをオススメします。
コンテスト応募作品へタグの登録後、タグの検索結果ページに作品が表示されているかをご確認ください。
「PLiCyゲームコンテスト2025参加作品」タグの検索結果に表示されていない場合、選考対象とならないことがあります。
- PLiCy に通常の手順でゲームをアップロード、もしくは作成をしてください。
- 応募作品のアドバイス
-
- 今回のPLiCy ゲームコンテストにおける選考基準についての軽い説明と選考を有利に進めるための注意点です。
評価点
「即死を連発する」「非常にテンポが悪い」場合は評価が特に低下します。
一方で、ゲームクリアまでに複数のルートが存在していると評価は上がります。
(一度プレイした後に別の方法でクリアを目指すなど遊び方が広がるため)
他にも以下の項に示す内容が主な評価点となっています。
最初から盛り上げていこう!
「開始数分で面白いと思えるか」は特に重要なポイントとなります。
ゲーム全体を通してみれば面白いゲームであっても、最初に受ける印象が良くなければ
その印象を覆す必要に迫られるというハンデが生じることになります。
例えばノベルの場合なら最初に「世界観を説明するための回想パートを設ける」、
「開始直後に何らかの事件を起こす」(寝坊して大慌てなどが典型例です)と言った細かい山場を持ってくる、
RPGやアクションの場合なら「そのゲームでできる面白い点を再序盤に示すこと」が重要です。
成長要素のあるゲームであれば成長させる、仕掛けを解くゲームであれば
仕掛けを解かせるといったことでゲームへの理解度を高めることができます。
簡単すぎ・難しすぎはNG
ゲームを作っていると、どうしても難しい場面ばかりに力を入れてしまいがちですが、
難しい場面は易しい場面があるからこそ目立つものです。
ゲームをつまらなくする要因の一つに「単調である」ということが挙げられますが、
これは簡単すぎる場面が連続している場合だけでなく、難しい場面が連続している場合でも同じことです。
ゲーム作りにおいて最も難しいことは「簡単なのに面白い場面」を作ることと言っても過言ではありません。
難しい場面の後にはほっと一息つける簡単な場面を用意するように心がけることが面白いゲームを作る上での一つのコツです。
簡単にクリアしてそうに見えても、簡単とは限らない
プレイ情報を確認したり、コメントを貰った際に、
簡単にクリアされているから、難しくしようと思ってしまうことがあります。
しかし、その人がクリアしたのは、何回もプレイをしているからだったり、
ゲームに慣れているからという可能性もございます。
たまたまその人がクリアしただけかもしれません。
重要なのは、「初めてプレイする人たち」にとって適正な難易度であるかです。
難易度調整の際は、その点を考慮して調整することをお勧め致します。
「面白さ」は時代で変化する?
ゲームをはじめとする物語や遊びには、その時代の流行などが反映されます。
これは時代ごとに人が「面白い」と感じる基準は変化することを意味します。
30年前に作られた物語、50年前に作られた物語を「古い物語」と感じるのはこれが理由です。
その為、昔に制作したゲームをそのまま調整せずに公開した場合、
今の時代・流行に合わないという理由で評価が伸びないこともあります。
(もちろん、時代を選ばない名作もたくさんあります)
コンテスト対策として、時代に合わせた変更(キャラクター、設定など)を考えてみても良いかもしれません。
PCとスマホ両方のことを考えてみよう
PLiCyにお越し頂いた方の環境は、32%がWindows、30%がAndroid、21%がiOS、8%がMacintoshになっております。(集計時点)
AndroidとiOSだけでも比率が半分を超えており、
10人に5人以上がスマートフォンで遊んでいるという計算になります。
スマートフォンユーザーの比率は年々上がり続けている傾向があり、今後も増加すると予想されます。
ゲームを公開する際はPCだけではなくスマートフォンのことも考えてみて、
実際に作ったゲームをスマートフォンでもプレイしてみるのが良いかもしれません。
また、新たにChrome OSによるアクセス率も伸びており8%に達しています。
主に若年層による利用が目立った形となっているようで、若年層へのアプローチをかける際にChrome OSの存在を意識する価値は高いと思われます。
RPGゲームにする理由を考えてみよう
ゲームの王道ジャンルとしてのRPGですが、RPGジャンルでゲームを作る理由を一度考えてみましょう。
プレイヤーに選択の余地がないゲーム進行になっていないか、ただ同じ場所を往復するだけになっていないか、ただ話を読ませるだけになっていないか……。
特にストーリーを重視したとき、なぜRPGを選ぶのか、なぜノベルではないのか、RPGならではの表現方法を取り入れてみましょう。
「稼ぎプレイ」を前提にしないように気をつけよう
ゲームにつきものの「稼ぎプレイ」ですが、稼ぎを攻略の前提にしたゲームバランスにはならないようにしましょう。
最短経路を通ることで(多少の運が絡みつつも)詰まることなく進めることができるようにした上でプレイスタイルの差が出るように調整することをオススメします。
「このゲームでRTA(リアル・タイム・アタック)をするならどうするか?」を考えてみると良いでしょう。
長編の場合はセーブデータの互換性を大切に
長編の場合は、アップデートの際にはなるべくセーブデータの互換性を持たせるようにしてください。
アップデートによってセーブデータが消えてしまうのはプレイヤーにとって辛いので、やり直すのを諦めてしまいがちです。
主人公や味方のナーフ(弱体化)はやめよう
ナーフは原則控えた方が良いです。
審査期間中にいいゲームバランスとして高評価であった作品が、ナーフアップデートによって評価が下がったという事例もあります。
リリース後のナーフは避けた方が良いかと思われます。
GDAやpli-log製のゲームは小分けにせず1つのゲームにまとめよう
短い1つのステージで構成されたGDAや、数会話で終わる極短編のpli-log作品を多数に渡って応募されることがあります。
審査における評価は個々のゲーム単位で行っており、ゲームの規模も少なからず評価点に含まれています。
GDAの複数マップ機能や中間ゴール機能を活用したり、オムニバス形式のノベルにするなどゲーム単体としての規模拡充を図ることを推奨します。
ゲームオーバーには基本的にならないようにしよう
ゲームオーバーはプレイヤーの大きな離脱点となりえます。
ゲームオーバーになるということは前回のセーブ時点からゲームオーバーに至るまでのプレイをなかったことにしてしまうことであり、そこまででゲームを面白いと思わせていなければプレイヤーがゲームをやめてしまうこともあります。
そのため、特に序盤においては原則ゲームオーバーにならないゲーム設計を心がけるようにしましょう。
ゲームオーバーになる状況は基本的に開発者の想定から外れた行動をプレイヤーが取ることで生じるものですが、いかに想定外の行動を取らせないか・どうすれば想定内の行動を取りたくなるかを考えてみるとよいかもしれません。
あえて容易に全滅が起こるゲーム設計にする場合、ゲームオーバーにしてタイトルに戻すのではなくペナルティなしで街へ戻されるようにする、数秒前の直前の選択肢に戻るなど、リスクなしで気軽に再チャレンジできる仕組みを導入してみましょう。
チュートリアルは丁寧に、且つ分散する
ゲームを作る上で最も重要といっても過言ではない点に、ゲームをプレイヤーに理解させることがあります。
機能を説明する際にチュートリアル画像をまとめて1回表示して終わりではプレイヤーは中々理解してもらえません。
チュートリアルの表示→実際に使わせるを1セットとして実装したほうがよいでしょう。
そのため、基本的にチュートリアルの説明は読み飛ばされるものと考え、プレイヤーに実際に操作させることで理解できる仕組みを整えることが大事です。
また説明の密度を下げることもポイントです。
例えば、戦闘の説明であれば属性相性や必殺技の使い方といった事柄も1つの戦闘の中でまとめてするのではなく、
弱点属性に関する説明だけの戦闘・必殺技を使うためだけの戦闘を何回にも分けるほうが理解しやすくなります。
- 今回のPLiCy ゲームコンテストにおける選考基準についての軽い説明と選考を有利に進めるための注意点です。
- ゲームクリエイターとストリーマーがより盛り上がる未来を目指して
-
PLiCyゲームコンテストの開催も今回でついに11回目となり、ここまで支えていただいた皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
PLiCy運営スタッフ一同、これからもコンテストを持続して開催できるように努めて参ります。
さて、昨年に行いました新たな試み「フリーゲームグッズ化計画」。
クラウドファンディングを用いてフリーゲーム作品のグッズを返礼品として皆様に届ける本企画が、パワーアップして開催されることが決定いたしました。
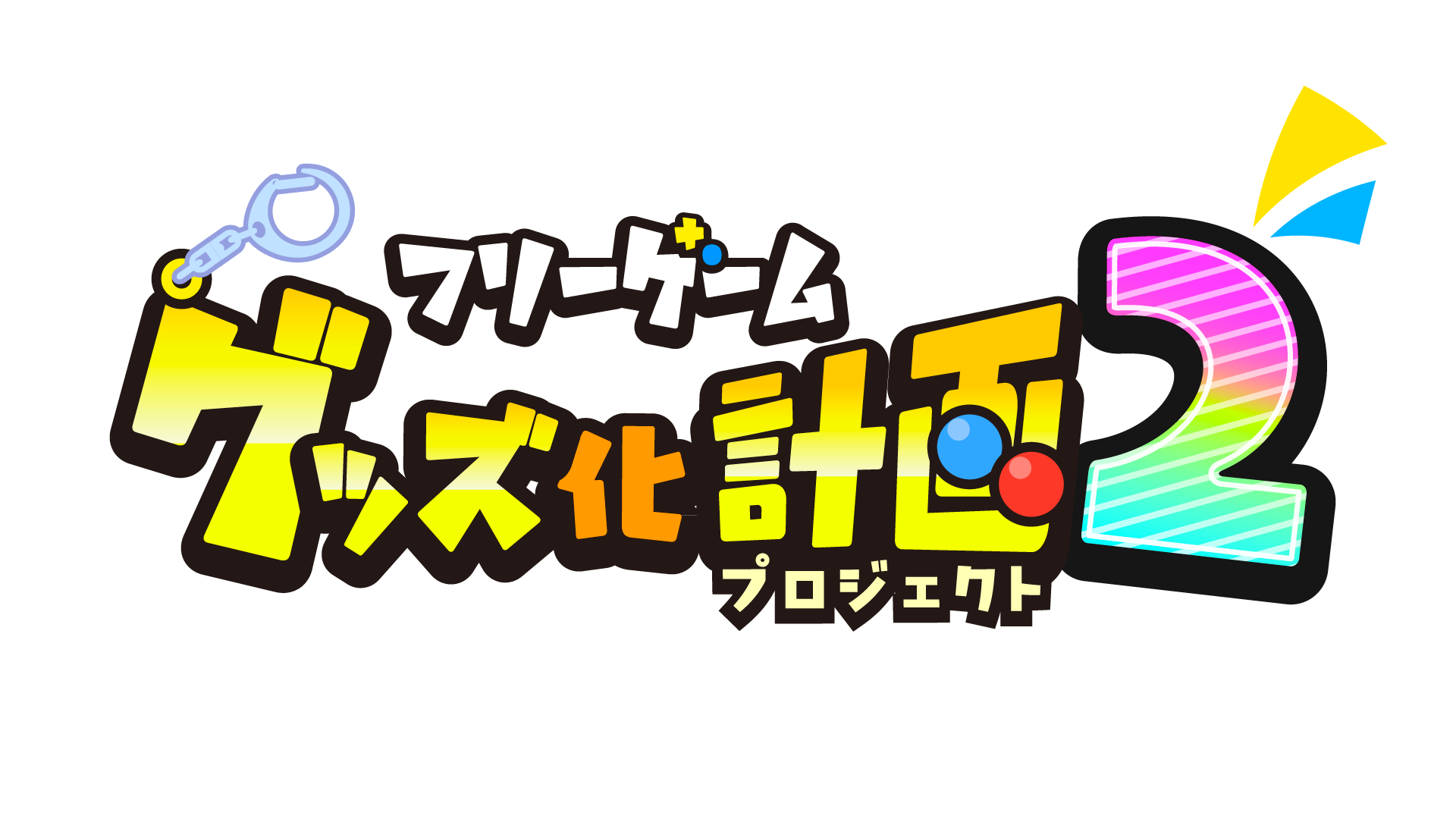
ゲームクリエイターとプレイヤーの双方が盛り上がれるお祭りとして発足したフリーゲームグッズ化計画。
まさかの2度目の実施ができることとなり、皆様に応援していただいたおかげで去年よりも規模を拡大しての開催となりました。
ゲームクリエイターだけでなくストリーマーを加え、フリーゲーム文化を広げる新たなクラウドファンディングサービス・PLiCy Plusを展開いたします。
PLiCyプラスのコンテンツ第一弾として開かれる「フリーゲームグッズ化計画2」をどうぞよろしくお願い申し上げます。
- 受賞作品の商品化事例
-
- 過去のコンテストで受賞した作品が商品化された事例です。
ヘルズ・ハイ・ハーモナイザーズ

Nintendo Switch版ヘルズ・ハイ・ハーモナイザーズ販売ページ
PLiCyゲームコンテスト2018の受賞作品です。
独特なシステムと雰囲気を持っており、作者様の精力的な活動によりSwitchでの発売に至るだけでなく以降も多くのアップデートが行われています。
また、Steamでのリリースも準備を進めています。ぜひSteam版ヘルズ・ハイ・ハーモナイザーズのストアページをご覧ください。
探光エスパシオ

Nintendo Switch版探光エスパシオ販売ページ
PLiCyゲームコンテスト2019のシナリオ部門銀賞と審査員賞に選出された作品です。
奇妙な世界観ながらも落ち着いた印象が特徴です。
Buddy Collection

Nintendo Switch版Buddy Collection if -宿命の赤い糸-販売ページ
PLiCyゲームコンテスト2016のライター部門で金賞に選出された作品です。
演出やキャラクターの表現が細かく作り込まれており、
また制作陣の継続的な開発意欲の高さもあってSwitchへの移植が実現しました。
- 過去のコンテストで受賞した作品が商品化された事例です。
- 応募してはいけないものは?
-
以下に該当するゲームはコンテストの受賞対象外となります。
- 第三者の著作権やライセンス等を侵害しているもの
- 他者への誹謗中傷などの権利を侵害しているもの
- 日本国法において違法性がある表現を含むもの
- 過去のPLiCyコンテストで応募しているもの
- 内容にあからさまな性的表現あるいは過度な暴力表現を含むもの
- 応募するにあたっての注意事項
-
- 応募された作品はPLiCy及び運営プロジェクト側が紹介・宣伝に使用させていただく場合があります。
- 作品紹介の際に応募者のユーザーネームを表記させていただきます。
ユーザーネーム以外の個人情報につきましては原則として公表することはありません。
- 審査スケジュール
-
- 4/24 クラウドファンディング開始&PLiCyゲームコンテスト2025募集開始
- 6/30 クラウドファンディング締切
- 8/31 PLiCyゲームコンテスト2025締切
- 9/30頃 クラウドファンディング返礼グッズ発送完了予定
- 11/1 コンテスト本審査開始
- 12/14頃 受賞通知予定 ※1
- 12/23 PLiCyゲームコンテスト2025結果発表予定 ※2
- 2/20頃 受賞賞品発送完了予定 ※3
- ※各日程は諸般の事情により変更される可能性があります。予めご了承ください。
提出期限2025年8月31日24時を以て応募を締め切った後、3ヶ月~4ヶ月程度が審査期間となる予定です。
その後、受賞者の方へは受賞者コメントなどのため追って連絡を差し上げることとなります。
受賞の通知を受けた方は、結果発表日の前日までに受賞コメントをご連絡頂きますようお願い致します。
※1 ※2 ※3 応募作品数によって審査スケジュールが大きく遅れる可能性があります。遅れが見込まれる場合には事前に告知をいたしますが、何卒ご了承いただければ幸いです。
- 応募される方へのお願い
-
応募作品の取り扱いについて
コンテストは、多くのユーザー様のご参加により初めて開催できるイベントです。
コンテスト後に参加したゲームが削除されますと、
コンテストの参加者や、コンテストを見に来た方が混乱してしまう可能性がございます。
そのため、コンテストに参加をした場合は基本的に削除を行わないようご協力をお願い致します。
(禁則事項ではございません)
また受賞作品については、なるべく作品内容を保全し多くのユーザー様に遊んで頂きたいと思っておりますので
受賞作品のみ、
・作品の削除
・更新による「ゲーム内容の白紙化」「システム削除」
を禁止させて頂きます。
追加・修正については問題ございません。
受賞通知から結果発表まで
PLiCyでは、受賞コメントを掲載させて頂いております。
受賞通知後、運営プロジェクトから受賞コメントをお伺いさせて頂いておりますが、
結果発表までご返答がない場合はコメント無しで掲載をさせて頂くことになります。
賞品授与にあたって
PLiCyは、過去のコンテストでも賞品を授与させて頂いている実績がございます。
コンテストの賞品の授与の際は、PLiCyは受賞者全員のスケジュールを調整しなければならないため、
賞品の授与までに少々時間がかかることがございます。予めご了承ください。
また、結果発表後も一切ご連絡が無かった場合は
賞品の授与を中止させて頂くことがございます。
- 金賞(各部門1名ずつ)
- Amazonギフトカード 15,000円分
- 銀賞(各部門1名ずつ)
- Amazonギフトカード 5,000円分
- 銅賞(各部門1~2名ずつ)
- Amazonギフトカード 3,000円分
- ファイナリスト賞
- Amazonギフトカード 1,000円分
- ksg・バカゲー賞
- トイレットペーパー50ロール~80ロール
- 審査員賞について
-
- 審査員による特別賞を予定しています。
- 受賞の際にはPLiCy内のメッセージ機能にて連絡をいたしますので、ご登録されたメールアドレスのメッセージ受信通知をご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 通知から1週間ほどの間にご連絡が付かなかった場合、取り下げられる場合がありますことをご了承願います。
- 本審査の審査員一覧(敬称略)
-
- ・PLiCyスタッフ
- 他未定
- 協賛について
-
PLiCyフリーゲームグッズ化計画2
PLiCyゲームコンテスト2025では、去年と同様にクラウドファンディング フリーゲームグッズ化計画2で協賛を募集しております!
コンテスト運営費用をクラウドファンディングで募集しており、返礼品にはフリーゲームの限定グッズがございます。
ぜひともご支援のほど宜しくお願い致します!
- Q. すでに投稿してる作品を登録しても大丈夫?
- 今回の公式ゲームコンテストについては過去に投稿された作品を登録しても問題ありません。
- Q. 複数人数による共同作品の場合はどうすれば?
- 代表者の方を1名決めていただき、その方名義で投稿・登録をしてください。
- Q. 応募した場合に著作権はどうなりますか?
-
PLiCy 公式ゲームコンテストへ応募することによる著作権の変移は行われません。
プログラムや音楽、画像、動画などの著作権は、著作者が持ちます。 - Q. 複数アカウントで別々の作品を公開してもよろしいでしょうか?
-
作品ページにて記述をして頂くという場合に限り可能です。
故意ではなかったとしても、アカウント分散は複数の受賞を狙う行為と認識される可能性が高いです。
他のユーザー様にもご迷惑がかかりますので禁止とさせて頂きます。
- Q. 過去にフェスに登録し忘れてしまったゲームは大丈夫?
-
過去のゲームコンテストにて、タグ登録しているにも関わらずフェスに登録していなかったゲームが複数ありました。
フェスに登録されていないゲームは、過去のコンテストに参加できておりません。
それらゲームは今回のコンテストに参加可能です。 - Q. 複数の作品をPLiCyゲームコンテストに応募してもいいでしょうか?
-
問題ありません。
ただし、授与される賞におきましては原則として一人一作品とさせていただきます。 - Q. 総合順位が上位でも、人気部門だと受賞から外れることはありますか?
- 結果次第ではございますが、部門ごとに枠がございますので、枠からあふれた場合は上位でも受賞対象外になることがございます。
- Q. 他のコンテストに投稿したゲームを応募できますか?
-
問題ありません。
ただし、より多くの作品を知って頂くきっかけにする目的がありますので、
過去に受賞経験があるゲームより受賞経験が無いゲームを
優先して評価することがございます。
その点につきましてはご容赦ください。
また、作品にはその時代の流行なども影響されますので、
新しく作られた作品のほうがコンテストに適している傾向はございます。
- Q. 許可を得た二次創作物の投稿は可能ですか?
-
問題ありません。
ただし、オリジナリティも選考の対象となっております。
- Q. 前回のPLiCyゲームコンテストで応募した作品を再応募してもいいの?
-
PLiCyゲームコンテストで入賞しなかった作品に限り、内容の明確な更新があれば再応募可能です。
しかしながら、不十分な状態・未完成で出したことを考慮しての再応募許可ですので、
変化に乏しい場合は受賞する可能性は極めて低いです。
- 開催会社概要
-
浮田建設株式会社
事業内容
●特定建設業
●特定建設業
●一級建築士事務所
●届出電気通信事業者
●インターネット事業
所在地 岡山県津山市山下5番地
代表者 代表取締役 浮田佐平
電話番号 0868-22-2151
FAX 0868-24-1189